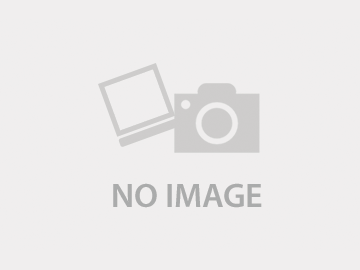【ブックカバーチャレンジ】NO.1
『生きがいについて』神谷美恵子、1966年刊行
読書文化の普及に貢献するため、好きな本を説明なしで表紙の画像だけ投稿する7日間のブックカバー・チャレンジのバトンを受け取りました。
人生の岐路に佇み悩んだ時、悲しみ、痛み、喜び、いろいろな場面で一冊の本が支えになり、一冊の本に導かれ、一冊の本から学んできました。良書は、人生に携える杖のようなものだと感じています。
今年7月に開催する予定で準備を進めていた展覧会「長島愛生園の人びと」、去年1月に会場が決まり、準備を進めてきました。長島愛生園での準備途上では、若い方々に「隔離」と言う言葉の意味がわかるだろうか、どう伝えようかと議論になりましたが。
3月には学校は休校になり卒業式は中止、4月に入り、入学式も中止、コロナ感染拡大により、会場となる場所が7月末まで閉館になり、展覧会は、延期となりました。
ダイアモンドプリンセス号では船内に「隔離」され、連日報道されていたニュースを見たのは2月でした。ちようど2月末に長島愛生園に滞在し、展覧会の打ち合わせしていた自治会の会議室で入所者の方々と一緒に見ていました。
入所者の方々の思いは複雑で、健康な人もみんな船から出る事が難しく、それを外から見ている私達は、心の片隅で、出てこないで欲しいと思っているような気配があるのではないか。
菌をもってるかわからない人まで出てこないで欲しいと内心思ったりすること、それが差別につながっていくんだと。自分が隔離される立場にもなりうる事まで考えが及びません、
まだ解明されてない未知の菌に対する恐怖心や警戒心が知らず知らずに差別を助長していきます。
ハンセン病も薬もない、治療法もまだ確立されず、昔は、遺伝などとも言われたりしていた時期がありました。
日本でコロナが感染拡大し始めた時から3ヶ月を経て、今、「自己隔離」などの言葉も日常生活でも使われるようになり、「隔離」と言う言葉を聴かない日がないほどになりました。2月では考えられなかった現実が次々と与えられてきました。
7月の展覧会が予定通りに開催されていたら、おそらく、今頃は準備に追われていた事と思います。
コロナによる自粛期間、改めて、いろいろ考える時間、本を読む時間が与えられました。
長島愛生園に研究調査として通うようになってからは10年、その手がかりとなったのは、一冊の本、神谷美恵子の『生きがいについて』でした。
『生きがいについて』が初版刊行されたのは1966年です。刊行から50年以上経た現在も読み継がれている名著です。
『生きがいについて』が刊行されたのは、神谷美恵子が長島愛生園に精神科医として通っている時期でした。
神谷が長島愛生園に精神科医として通うようになったのは、1957年から行った精神医学調査がきっかけでした。
実は、その前、戦前の1943年8月に12日間だけですが、東京女子医専からの見学実習の為に長島愛生園に滞在し、当時の療養所を身近で見てハンセン病医学の臨床の勉強をしています。
その頃、神谷は、ハンセン病研究者、大田正雄(木下杢太郎)の研究室に通って、ハンセン病の病原菌培養研究に取り組んでおり、菌の研究だけではなく、ハンセン病の療養所で臨床の見学をしたいと思うようになりました。そこで、ようやく、12日間の臨床見学実習の機会が与えられたのでした。
神谷の日記によると、東京から夜行寝台列車に乗り岡山に向かい、岡山からはまた1時間ほど列車に乗り、虫明港から船に乗って長島愛生園まで、当時、東京からは1日かかって、ようやく到着しています。
そして、戦後の混乱期を過ぎ13年ぶり、1957年に阪大精神科医局の精神医学調査の目的で再び訪れましたが、その時には、戦前の様子から一変し、近代的に様変りした長島愛生園の様子に神谷は非常に驚愕していました。
その調査の折、神谷は、当時、放置されていた精神科医療を目の当たりにしました。精神病を患っていた入所者がきちんとした精神科の治療を受けられずに、その上、ハンセン病の治療も受けてない状況を目の当たりにし、非常にショックを受けました。
そこで、精神科医療の整備を長島愛生園の高島園長に進言したところ、「それじや、あなた、やってください!」と神谷は頼まれてしまいました。新しい精神科医が見つかるまでと言う約束で神谷は長島愛生園の精神科医療を手伝いする事になりました。1958年9月、精神医学調査が終わる時期、若い精神科医が島の官舎に住み込み常勤勤務することになり、神谷はその若い医師に長島愛生園の精神科医療を託し、長島愛生園を後にしました。
しかし、その若い精神科医は10ヶ月後、突然辞めてしまいます。当時もまだ、ハンセン病に関わる医療者への偏見や差別もあり、その医師の母が「長島で働いていたら結婚に差し障るから」と言って官舎にやってきて連れ戻したと言うことでした。
1960年代になってもまだハンセン病についての差別、ハンセン病医療に関わる仕事をする方々への偏見、差別はありました。
1959年7月に精神科医のいなくなった長島愛生園にまた再び神谷は通うことになってしまいました。そして、1960年代も通い続けることになりました。
1960年代は日本もまだ社会制度や法律が整う時代でした。戦後、1947年日本国憲法ができ、社会福祉制度に関する法律も、1947年児童福祉法を皮切りに1963年には老人福祉法、1964年には母子福祉法など、福祉6法もまだ整っていく途上でありました。一般社会でも、全国的に病院や施設が整備されていく時期でした。
そのような社会状況下、長島愛生園で仕事をする医師は常に不足し、1960年代の長島愛生園に1500人の入所者に対して、常勤医師は、わずかに4〜5人、慢性的な医師不足の問題を抱えている時期でした。ハンセン病は1割の方が失明される病気であり、療養所で眼科受診をする人は、常に毎日150人ほどいたとお聞きしました。眼科医は1名か2名でした。眼科医が不足している現状を嘆いて書かれた療養所の詩もあります。
1939年に39歳の若さで亡くなった長島愛生園の詩人として有名な明石海人も何度かの手術を経て、失明をしています。明石もまた、主治医であった林冨美子医師のことを詩に詠んでいます。林冨美子が九州の療養所に転勤になってからも明石海人は林に手紙を送っていました。
入所者にとって、自らの病を診てくれる医師は、どれほど、大切であったかを知る手がかりになります。
神谷が大学の同窓会の会報などを通じて長島愛生園で仕事をしてくれる精神科医を募集してもなかなか人が見つかりません。ようやく1962年に応募して来られたのが高橋幸彦医師でした。結局、神谷と2人での交代勤務が続きますが、高橋医師は先にやめてまた神谷は1人勤務になり激務が続いていきましたが、ついに神谷は虚血性心疾患の体調不良を抱え、長島に通うことが出来なくなり、1972年退職をする事になりました。精神医学調査から15年経っていました。
話しを本に戻しましょう。
『生きがいについて』の著書の中では、特に後半に長島愛生園で行った精神医学調査の資料が用いられています。
神谷が行った精神医学調査の男性軽症者180名のうち、半数以上が将来に希望をもってないと答えていました。
それが第5章の「生きがいをうばいさるもの」第6章の「生きがい喪失者の世界」にひかれています。
ハンセン病を宣告された時の心境も「目の前が真っ暗になりました」や「死の宣告を受けた絶望感」など絶望、悲観的なものが多かったのです。この入所者の回答から神谷は「生きがい喪失」をより深く考えるようになりました。
一方でハンセン病になった時の心境に
「よりよく人生を肯定するようになった」「心がゆたかになった」「心が高められ、人の愛、生命の尊さを悟った」など、生きがい喪失の闇の中から建設的な姿勢を持ち現世に戻ってくる姿も神谷は見たのでした。
それらが第7章「新しい生きがいを求めて」や
第11章「現世へのもどりかた」にひかれています。
このように、神谷が長島愛生園で行った精神医学調査が『生きがいについて』の大切な箇所に用いられています。その他、ハンセン病の療養所の文芸作品などもたくさん引用されています。前述した明石海人、玉木愛子、北条民雄などの作品もひいています。長島愛生園の経験が礎にあり、誕生した名著です。
神谷は、このようにハンセン病療養所の入所者の方々からたくさんの事を学び、受け取りました。
1979年10月22日65歳で急逝するときまで長島愛生園の事を思い、長島詩話会やハーモニカ楽団、盲人会など長島ダム生園の人びとと交流をしていました。
「ひとはそれぞれの生涯の中で、ちがった時期に、ちがった形で、人生の行く手にたちふさがるこの壁のようなものにつきあたり、その威力を思い知る。その時には必ず生きがいということが問題になるであろう。このような悲しみと苦しみにみちた人生もなお生きるのに値するかと。自分はこれから何を生きがいにしていったらよいのかと。
時代がどのように変り、政治形態や社会のしくみがどのように改変されようとも、人生のこの面はとりのぞくことができないのではないだろうか。学問や社会政策の進歩によって、病や老や死の脅威がどれほど遠ざけられたとしても、要するに相対的なことでしかありえない。
精神安定剤や麻酔剤で苦悩に対する感受性を低下させたり、精神賦活剤で元気をつけたとしても、結局はその場しのぎに過ぎない。」と神谷は記しています。
神谷が50年以上前に記した文章は、瑞々しく新鮮な感性で今の私達に寄り添い語りかけてくれます。
神谷は、若き日に結核に罹患した時、亡くなっていく人も多い中で何故、自分が生かされて、別の人が亡くなっていくのかと言う負い目がいつも心にあり、病による苦しみ、生と死の問題が若き時代から心をしめていたのでした。
『生きがいについて』の中にも記されていますが、「なぜ私たちではなく、彼らが病まなければならないのか」と言う言葉、神谷が亡くなるまで大事に問い続けていたことでした。
明日から神谷美恵子に繋がる本を紹介していきます。
️