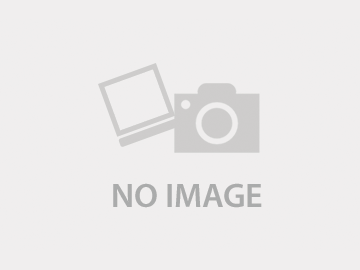【ブックカバーチャレンジ】NO.7、最終日
『新編、志樹逸馬詩集』志樹逸馬著、若松英輔編者、2020年1月刊行
『志樹逸馬詩集』(1960年)『島の四季』(1984年)が刊行されていましたが、2020年1月に若松英輔氏により編まれた『新編 志樹逸馬詩集』が刊行されました。
実は、それより前、1950年に『志樹逸馬詩集』が原田憲雄先生、原田禹雄先生の編集により刊行されていたが、すでに絶版になっていました。
今回の新編には今までに収録されていた詩に加え、ご遺族の協力で得られた志樹逸馬のノート60冊に及ぶ資料から未公開の詩も掲載されています。それに志樹の人生を辿る上で大変詳細な年賦が加筆されています。
1917年(大正6年)東北で、教育者の父のもと生まれ、1930年(昭和5年)9月にハンセン病と診断され、間もなく東京多摩全生病院に入院しました。
旧制中学1年に進んだ時期、左頬に赤い斑点ができ大学病院を受診、ハンセン病ではないかと診断を受けて、全生病院に行く事を勧められたのでした。
まだその時期、東京・公立療養所第一区府県立全生病院と呼んでいました。
長島愛生園など国立療養所が出来たのは翌年1931年のことでした。
病名の告知、病態の説明、現在の病状や予後、治療方針など、現在では当たり前になっていますが、1930年当時は、説明などが受けられる状況が少なかったと書いてあります。
これは当時としては珍しい事ではありませんでした。
ハンセン病が医学的、または、社会的にどんな病か分からず、家族や地域、職員の態度から
その病を患う事がどんな事かを幼い志樹自身が察していくしかなかった時代であったと。
志樹が初めて全生病院で療養をするようになったまだ、幼かった志樹は、みんなから「坊ちゃん」と呼ばれ、大変可愛がられました。
ハンセンの症状、障害の重さも様々でしたが、幼い志樹は、自分もやがて障害をもつかもしれないと、勉強や自分に与えられる仕事に打ち込んでいく決意をします。
1933年(昭和8年)長島愛生園に転園し、養鶏部に勤め、野菜作りや土に親しみます。そして、詩は1935年(昭和10年)18歳の時に初めて『愛生』に作品を発表します。
1942年(昭和17年)24歳の時、結婚。その頃から手足の麻痺が進行し、片足は麻痺してしまいました。曙教会で洗礼を受けます。
1943年には、病状は進み、両手が麻痺、全ての指が曲がり、作業中の出来た傷により、化膿し指を切断しなければならない状態になりました。
青い鳥楽団を作った近藤宏一さんは、道を挟んだ向かいの住宅に住んでいました。近藤さんは
志樹の奥さんの治代さんから点字を習ったのでした。それが近藤宏一が舌読で点字を読み、楽譜を読み、楽団を作る事につながっていったのですから、1人の人生の出会いは不思議だと感じます。
1945年、戦争は終わり、志樹も1949年からアメリカから入ってきたプロミン注射を受けるようになりました。しかしながら、それまでに障害をもって変形した身体、障害の状況は元には戻りません。
志樹は、1950年、生死を彷徨う状況が1ヶ月起こりました。その後、回復し、1953年35歳、ハンセン病療養費の詩集『いのちの芽』を刊行し、「黒人霊歌」「土壌」「代償」などが出来ます。
その後次々と作品を精力的に生み出していきました。
私が志樹逸馬の詩を初めて読んだのは神谷美恵子の「生きがいについて』にひかれていた「土壌」と言う詩でした。(下記抜粋参照)、この他にも、「丘の上には」「代償」が引用されています。
神谷美恵子『生きがいについて』より抜粋
⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎
たとえ独房の中で死と直面していようとも、肢体不自由の身で島に閉じこめられていようとも、自分の生は全人類の一部であり、自分は、
皆に対して意味と責任を担っているのだと思い至るとき、ひとはしっかりと顔をあげて堂々とその生を生き抜くことができる。少なくともその可能性は開かれている。
それは、はじめにでのべた一患者の詩「土壌」にもよくあらわれている。
わたしは耕す
世界の足音が響くこの土を
原爆の死を、骸骨の冷たさを
血の滴を、幾億の人間の
人種や 国境を ここに砕いて
かなしみを腐敗させてゆく
わたしは
おろ おろと しびれた手で足もとの土を耕す
泥にまみれる いつか暗さの中にも伸ばしてくる根に
すべて母体である この土壌に
ただ耳をかたむける
⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎
志樹逸馬も神谷の精神医学調査に答えた1人であり、1958年4月2日、神谷美恵子の精神医学調査報告会が長島愛生園大講堂で行われました。
神谷より書簡で依頼があり、回答をした志樹の文章は、『生きがいについて』の「はじめに」にひかれています。神谷はこの事がきっかけになり、志樹と交流し、亡くなる前にも神谷は志樹の部屋を訪ねていました。
1959年9月には結核菌陽性になり、肝臓、腎臓も悪くなり、詩の創作が出来ない状況になります。そして、12月3日、亡くなります。志樹42歳でした。
『新編 志樹逸馬詩集』の編者である若松氏は、「詩はあたまに届けるのではなく、心にそっと送り出さなくてはならない」
「知識をもった者が披瀝する知識よりも、苦しむ者が体現する苦しみに、知識を超えた叡知を観ること、見続けること、それが志樹逸馬が己れに求めた詩人としてのつとめだった。」と書いています。
ハンセン病の療養所に通っていた神谷美恵子、
長島に通っているうちに神谷自身、長島愛生園の療養所の人びとに支えられていたのだと思います。今まで、神谷美恵子は、隔離政策を肯定したなどと書かれていたりして批判をしている文章も散見していますが、よく調べてみたら、神谷自身、政策について書いている箇所は見当たりません。
そしてまた光田健輔医師の弟子とか誤解されていますが、神谷は、らい菌培養研究の大田正雄の研究室で学んでいました。光田の弟子と言う書き方は誤解です。光田は1876年生まれであり、医学については済生学舎で学んでいます。同期には、野口英世がいました。
神谷が1943年に実習に行った時には既に初老の67歳、精神医学調査の途上1957年に光田は81歳で退職します。光田とはほとんど交流はありませんでした。これは、光田健輔を最後まで介護した三男の横田篤三の妻である故・横田百合子さんに9年程前に出会ってお話をお聴きした時にも、神谷との個人的な交流はなかったと言われていました。
そしてまた、神谷美恵子が療養所をユートピアのように描いたと書いて批判している方もありました。『生きがいについて』をしっかり、読み込んだ研究が薄い為にこのような解釈が生まれてしまっています。
私は、逆にユートピアではなく、ハンセン病の病の壮絶な状況を神谷著作から学びました。
神谷美恵子の実践の具体的な実際が著作には記されており、その裏をとる為に診療録調査をすることになりました。9年程前の事になります。
そこで、ハンセン病の医療や薬の事をご教示、ご指導をいただきましたのが、ハンセン病専門医師の尾崎元昭医師でした。1969年から長島愛生園に勤務されており、神谷と同じ時期に仕事をされていた医師であり、現在も長島愛生園に仕事をされています。1960年代の療養所の現場を知っておられる貴重な日本のハンセン病の専門医のお一人です。
戦後ブロミンが入り、ハンセン病は治る病と言われるようにはなりましたが、志樹逸馬も1959年に亡くなっています。1960年代は、プロミンの薬剤耐性菌問題が起き、また重症化したりする方々もありました。
そのような療養所の実際の状況を知ると、
現場で最前線でハンセン病医療に関わる人自身も壮絶な現場であった事なども伺い知る事が出来ます。
神谷の実践については、細かく読んで調べていけばわかる事なのですが、批判する人は批判する場所しか読まれないので、偏りのある視点になってしまいます。
今、コロナ医療の現場で仕事をしている医師は
本当に大変な状況で、コロナの政策や医療施設など決めているのは厚生労働省や政治家。
そんな構図は昔からあまり変わっていません。
神谷の葬儀に読まれた長島愛生園の島田ひとしの詩「先生に捧ぐ」に込められた想い「そこには1人の医師がいた」の通り、15年通っていた医師の1人であったのだと思います。
以前、書きましたが、神谷自身、自分はらいに何もしてこなかったと。島に住みこんで仕事をする医療者の方々の事に敬意を表しています
7日間のブックカバーチャレンジでは、神谷の「生きがいについて』を手がかりに7冊の本を紹介しました。
『生きがいについて』の参考文献だけでも
200冊近くの文献にのぼり、関係資料を加えてたら膨大な数になります。一冊ずつが貴重な著書であります。
今回は、私の身近な7冊に絞り込みました。
自分でも2016年3月に提出した博論「神谷美恵子の実践の研究」を違う視点からみる新しいきっかけになりました。
人々から忘れ去られようとしているハンセン病の重荷、近代日本の歴史の中で、病気を背負って苦しんできた人びとの存在を忘れ去られてしまわないように、神谷美恵子が読み継がれる『生きがいについて』に託した事を改めて考える時間ともなりました。